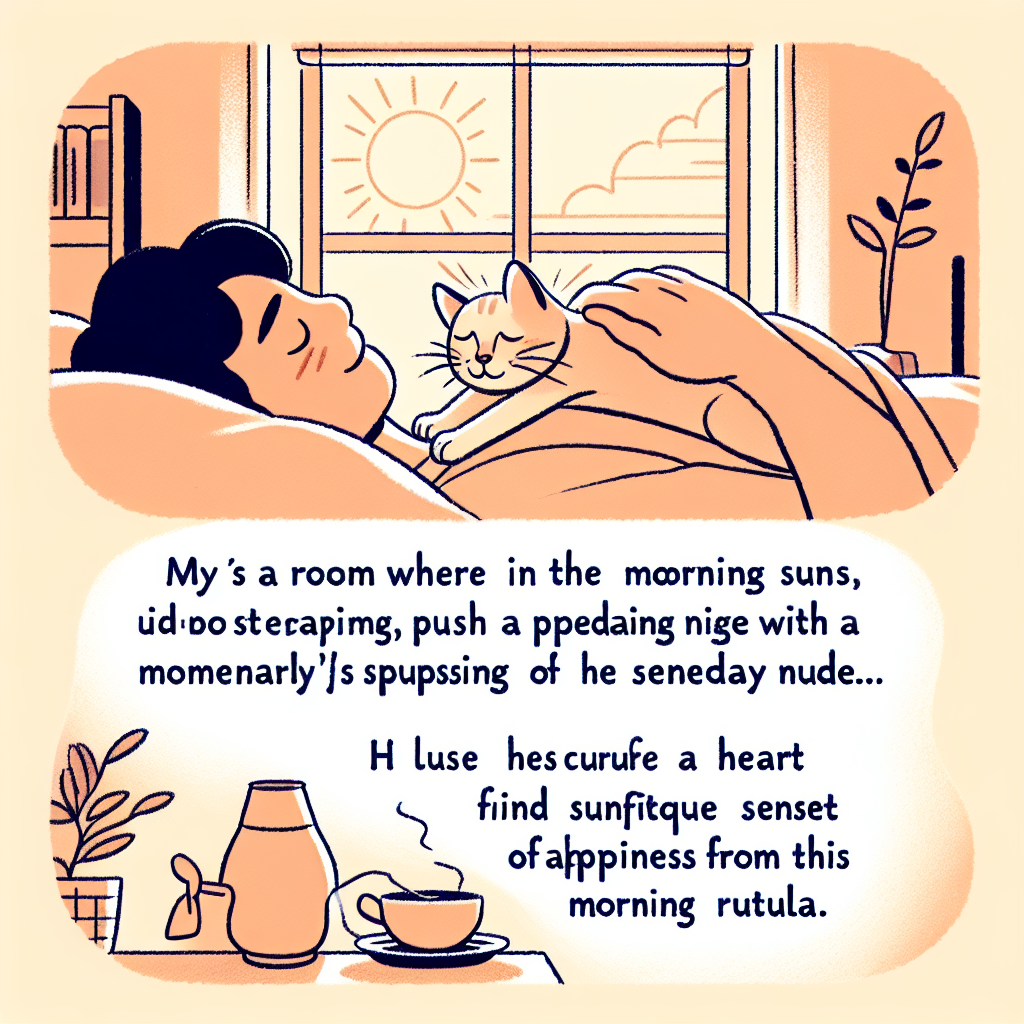
窓から差し込む朝日が、うっすらとカーテンを通して部屋を柔らかく照らしていた。私は心地よい眠りの中で、まだ少しだけ夢の続きを見ていたかった。布団の中は適度な温かさで、外の世界から完全に遮断された安全な居場所のようだった。
そんな穏やかな朝の静寂を破ったのは、軽やかな足音だった。最初は小さな物音程度にしか感じなかったが、次第にその存在感が大きくなってきた。ベッドの上を歩く振動が、私の意識を少しずつ現実へと引き戻していく。
「にゃあ」
甘えるような声と共に、私の顔の近くに温かい息遣いを感じた。目を開けると、そこには我が家の猫のミルクが、琥珀色の瞳で私をじっと見つめていた。朝の光に照らされた彼女の目は、まるで宝石のように輝いている。
「まだ早いでしょ…」
私が毛布にもぐり込もうとすると、ミルクは小さな前足で私の頬を優しくタッチしてきた。彼女なりの起こし方だ。朝の餌の時間まであと30分はあるはずなのに、この可愛らしい催促には逆らえない。
ミルクは私の反応を見て、さらに大胆になった。今度は私の髪の毛で遊び始め、時々耳元でゴロゴロと喉を鳴らす。その振動が心地よく、かえって眠くなってしまいそうだ。しかし、彼女はそれを許してくれない。
私が再び眠りに落ちそうになると、今度は布団の上で回転を始めた。ベッドが揺れる度に、私の意識は現実に引き戻される。彼女の毛並みが私の腕に触れる度に、くすぐったさを感じる。まるで小さな目覚まし時計のように、確実に私を目覚めさせようとしている。
「わかったわかった、起きるから」
諦めて体を起こすと、ミルクは満足げな表情を浮かべた。私の膝の上に飛び乗り、尻尾を高く上げて顔を擦り寄せてくる。この愛らしい仕草に、朝早く起こされた不満も吹き飛んでしまう。
窓の外では、早起きの小鳥たちがさえずりを始めていた。ミルクはその音に反応して耳をピクピクと動かし、窓辺に駆け寄る。朝日に照らされた彼女の姿は、まるで絵画のように美しい。
私はベッドから降りて、彼女の後を追う。キッチンに向かう途中、ミルクは何度も振り返りながら私の足元にまとわりつく。まるで「早く早く」と言っているかのように。
この日課は、実は私にとって大切な朝の儀式となっていた。眠りを妨げられることに最初は戸惑いを感じていたが、今では彼女との静かな朝の時間が楽しみになっている。
キッチンでミルクのフードを用意しながら、彼女の待ちきれない様子を眺める。食器を床に置くと、彼女は嬉しそうに食べ始める。その姿を見ていると、私も自然と微笑んでしまう。
朝食の準備をしながら、窓の外を見る。街はまだ静かで、朝もやが建物の間を漂っている。ミルクは食事を終えると、窓辺の日向ぼっこスポットに移動した。そこで毛づくろいを始める彼女の姿は、まるで優雅な貴婦人のよう。
この朝の光景は、毎日同じように見えて、実は少しずつ違う表情を見せてくれる。時には雨の日もあれば、曇りの日もある。でも、ミルクの起こし方は変わらない。彼女なりの愛情表現なのかもしれない。
ベッドに戻ると、さっきまで私が寝ていた場所にはまだ温もりが残っている。ミルクも日向ぼっこを中断して、再び私の元へやってきた。今度は甘えるように膝の上で丸くなり、幸せそうに目を細める。
彼女の柔らかな毛並みを撫でていると、不思議と心が落ち着く。猫は人間の心を癒す力を持っているという話を聞いたことがあるが、まさにその通りだと実感する。ミルクの存在は、私の日常に温かな彩りを添えてくれている。
時計を見ると、もう出勤の準備を始める時間だ。ミルクはそれを察したかのように、私の膝から降りて、いつもの場所で見送りの態勢に入る。出かける前の最後の挨拶をすると、彼女は小さく鳴いて返事をする。
この朝のルーティンは、私とミルクにとって特別な時間となっている。たとえ眠りを妨げられることがあっても、彼女との穏やかな朝のひとときは、一日の始まりにふさわしい素敵な贈り物だ。
夜、仕事から帰ってくると、ミルクは玄関で待っていてくれる。また明日の朝、彼女の可愛らしい目覚まし係に起こされることを思うと、少し楽しみになってくる。そして、また新しい一日が始まるのだ。
人生には予期せぬ出来事がたくさんあるが、ミルクとの朝の時間だけは変わらない。それは私たちだけの小さな幸せの儀式。たとえ眠くても、彼女の愛らしい瞳を見れば、すべての疲れが癒されていく。これからも、この特別な朝の時間を大切にしていきたい。


コメント